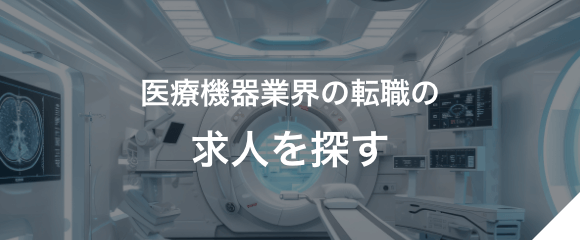医療機器分野別 治療と製品
2025/06/25
2025/07/16
目次
医療の現場では、様々な検査・診断・治療に対応した医療機器が使用されています。それらには改良が重ねられ、新しい治療法とそれを可能にする機器の開発が日々進められています。ここではその一部をご紹介しています。
PCI・末梢血管インターベーション
PCI:Percutaneous Coronary Intervention(経皮的冠動脈形成術)とは虚血系心疾患に対するカテーテルを用いた治療法です。(以下:PCI)
心臓を栄養する血管を冠動脈といいます。冠動脈は4mm程度の細い血管であり、心臓を動かすために血液や酸素などを供給しています。動脈硬化により冠動脈が狭くなった状態を狭窄と呼び、狭窄により引き起こされる症状を狭心症といいます。
また、血栓などで完全に詰まってしまうことを心筋梗塞と呼びます。冠動脈に流れる血液量が狭心症や心筋梗塞により低下または遮断されることで胸痛や息切れなどの虚血症状が現れます。最悪の場合、心筋の壊死を引き起こし心停止など死につながります。
PCIはまず、足の付け根や手首にある太い動脈にシースと呼ばれる筒状の短い器具を挿入し動脈への入り口を確保します。そのシースの中にガイディングカテーテルと呼ばれる細い管を使い動脈内に沿わせ冠動脈の入り口まで進めます。ガイディングカテーテルの中に0.014インチ(約0.36mm)と非常に細いガイドワイヤーと呼ばれるワイヤーを挿入し冠動脈内の狭窄部位(治療箇所)まで進めます。ガイドワイヤーにバルーンカテーテル(風船)と呼ばれるものを乗せ冠動脈内で膨らませ血管の内側から狭窄部位を押し広げます。
広げた冠動脈が再び狭くならないようにステント(金属メッシュ状のチューブ)を冠動脈に留置します。さらに近年ではステント表面に再狭窄予防の薬が塗布されたDES(Drug-Eluting Stent)やバルーンカテーテルに再狭窄予防の薬剤が塗布されたDCB( Drug-coated Balloon)が登場し再狭窄率は5%程度となっています。また、動脈硬化が進行し石灰化と呼ばれ狭窄がバルーンカテーテルで広げるのが困難な場合はアテレクトミーデバイスを用いて石灰化を破砕したり血管の内壁からプラークなどを直接削ぎ取る方法もあります。
PPI:Percutaneous Peripheral Intervention(経皮的末梢血管形成術) とは心臓から離れた場所にある腕や足を通る血管や透析用のシャント、頸動脈、腎動脈など全身の末梢血管に対するカテーテル治療の事です。
生活習慣病が原因で腕や足の動脈硬化が進行すると、動脈内に脂肪やコレステロールが固まってプラークができ、血流が悪くなります。腕や足の血流が悪くなると、疲労感、しびれ、冷たい感覚、指先の痛みなどの症状がでます。重症の場合、血管が閉塞しその先の細胞が壊死し、切断に至ってしまうことがあります。
心臓カテーテル同様、足の付け根や腕の動脈などからカテーテルを挿入しガイドワイヤーに沿わせバルーンカテーテルを使用し血管内から狭窄部を押し広げ血流を確保します。 バルーン拡張後、拡張部が再び狭くならないようステントを体内に留置してカテーテルを体外へ抜去します。 また近年ではPCI同様、薬剤溶出ステント(DES)・薬剤塗布バルーン(DCB)などもあり治療の選択肢が広くなっています。
脳血管インターベンション

脳血管インターベンションは、足の付け根の動脈(大腿動脈)からカテーテルを挿入し、X線透視下にて血管の形や走行を確認しながら目的部位までカテーテルを誘導して治療を行います。治療の目的によってプラチナ製コイル、液体塞栓物質、バルーンカテーテル、ステント、血栓回収用ステントリトリーバーなど様々なカテーテルを用いて治療を行います。
未破裂脳動脈瘤
動脈瘤の中にプラチナ製コイルを留置して瘤の中を充填し、出血を予防する治療です。最近では、更に進化しFlow Diverter(血流分流デバイス)の導入が増加しており、その後、プラチナコイル併用による遅延破裂リスク低減を検討する事例も報告されています。
破裂脳動脈瘤 (くも膜下出血)
くも膜下出血を起こす原因のほとんどが脳動脈瘤の破裂によるものです。脳動脈瘤は破裂しても一旦は血栓がかさぶたのように破裂部をおおいますが、動脈瘤が再破裂してしまうと30~50%の確率で命を落とします。早期にコイル塞栓術にて再破裂(再出血)予防の治療を行います。
硬膜動静脈瘻の塞栓術
硬膜周囲で異常な動脈と静脈が直接つながり、脳出血や脳症状、けいれんなどを起こします。脳血管インターベンションで動脈あるいは静脈経由に病変部を塞栓し、異常な流れを閉塞し治療します。
脳腫瘍の塞栓術
大きな出血をしやすい脳腫瘍には、栄養血管を閉塞させることにより、開頭術中の出血を減らす目的で治療を行います。
頚動脈狭窄症
頚動脈にできた血管狭窄にできた血栓やプラークが原因で、手足の麻痺や言語障害といった脳梗塞(のうこうそく)の症状を来すことがあります。このような頚動脈狭窄症に対しバルーンカテーテルを用いて拡張術、頚動脈ステント留置術にて治療します。
急性期脳梗塞に対するカテーテルを用いた血栓回収療法
2010年に急性期脳梗塞に対して 血栓回収カテーテルが保険認可され、2011年には血栓吸引カテーテルも承認されました。2015年には,治療の有効性を示す論文が複数発表され,急性期脳梗塞治療の必要性が高まっています。脳血管に詰まった血栓に対しステントリトリーバーを用いて血栓回収を行い、脳血管の血流を再開通させる治療です。
CRM(Cardiac Rythm Management)・EP(Electrophysiology)
不整脈とは心臓の電気系統に異常が生じ、心臓が収縮する速さやリズムに乱れが生じる状態です。不整脈の診断には、心電図などの他、心臓電気生理学的検査(Electrophysiological Study:EPS)が行われます。この検査により、不整脈を引き起こしている原因や心臓の刺激伝導系のどこに異常があるかを調べます。方法は、数ミリ径の細い電極カテーテルを、足の付け根などの血管から心腔内に挿入し、様々な部位からの電位記録と電気刺激を組み合わせ、解析装置で解析することによって診断します。
各疾患や、症状により以下の代表的な治療が行われることがあり、使用する医療機器が異なります。
*薬物治療との併用や経過観察の場合もあり、すべての疾患に下記治療法が適応されるわけではありません。
不整脈アブレーション治療とは心臓の電気信号が乱れて起こる「不整脈」を治すために、異常な電気の流れを生む心筋の一部を熱や冷気、電気パルスなどで処置する治療法です。薬で改善しない場合に用いられ、根本的な治療が期待できます。全体の症例数は国内でも10万例を超え、成長市場として全世界含め注目されています。以下の3つが代表的な手技となります。
1.カテーテル・アブレーション:カテーテルを足の付け根などから心臓に通し、高周波の熱で不整脈の原因部位を焼く治療です。薬が効かない場合に有効で、体への負担が少なく、短期入院で行えることもあります。
2.クライオアブレーション:冷却したバルーン型の器具で心臓内の異常部位を凍らせて治す治療です。広範囲を一度に処置でき、組織へのダメージが少なく、安全性に優れています。
3.パルスフィールドアブレーション(PFA):電気パルスで異常な細胞のみを壊す最新の不整脈治療です。正常な組織を傷つけにくく、治療時間が短く、安全性も高いため、今後の普及が期待されています。
ペースメーカは、徐脈性不整脈(脈が遅くなる不整脈)の治療に使用されます。本体(電気パルス発生装置:Pulse Generator)と心筋を収縮させる為の電気刺激を伝えるためのリード(電極)から構成されており、心拍数を正常に維持する為の治療医療機器です。
年間で新規患者への植え込み手技と、本体の交換手技を合わせて約6,3万件の手術が国内で行われています。
ICD(植え込み型除細動器:Implantable Cardioverter Defibrillator )は心拍数を監視し、致死性不整脈(心室細動・心室頻拍)が起こると状況に応じた治療を自動的に行う機器で、体内に植え込まれます。治療の後に徐脈を呈する事があるので、ペースメーカの機能を兼ね備えています。
年間で新規患者への植え込み手技と、本体の交換手技を合わせて、約6,500件の手術が国内で行われています。
CRTとは「心臓再同期療法」の意味で、何らかの障害により心室の電気信号の伝わり方にずれが発生してしまった状態に対し、心臓の左右両心室から同時に電気刺激を与えることにより心臓の収縮のずれを同期させ、機能・症状を改善するものです。CRT-Dとは、CRT(心臓再同期療法;両心室ペースメーカ)とICD(植え込み型除細動器)の両方の性能を有するものです。
年間で新規患者への植え込み手技と、本体の交換手技を合わせて、約3,500件の手術が国内で行われています。
心臓外科手術・SHD(Structural Heart Disease)インターベンション

【心臓外科手術】
心臓外科手術には狭心症・心筋梗塞を対象疾患とする冠動脈バイパス術、弁膜症を対象疾患とする弁置換・形成術、大動脈瘤や大動脈解離に対する人工血管置換術、先天性心疾患に対する手術などがあり、様々な医療機器が使用されています。
冠動脈バイパス術は動脈硬化などによって狭窄した冠動脈に対して胸や腕、下肢などの血管をバイパスとしてつなげる手術です。
弁置換術は先天異常や高血圧、大動脈瘤などによって、弁が機能しなくなり血液が逆流するのを防ぐために人工弁と交換する手術です。人工弁には機械弁と生体弁があります。弁形成術とは人工弁に交換せずに自己弁の残存機能を生かすものです。
動脈硬化などによって引き起こされる大動脈瘤(大動脈が風船のように拡張するもの)や大動脈解離(大動脈壁の裂け目に血液が流れ込み血管内腔が2つになるもの)に対しては、病変部分の血管を人工血管に置換して治療します。大動脈だけではなく末梢血管用の人工血管もあります。
また、開胸・開腹せずに動脈瘤を治療するステントグラフトというデバイスも使用されています。これは人工血管にステントという金属の筒を取り付けたもので、小さく折りたたんで末梢血管から挿入した細い管から病変部まで進めて留置するものです。
【SHDインターベンション】
SHDとは「Structural Heart Disease」の略で構造的心疾患を指します。近年、SHDに対するカテーテルを用いたインターベンション治療が注目を集めており、エビデンスの集積とともにその需要は拡大しています。その中でも、重症大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療(TAVI: Transcatheter Aortic Valve Implantation)の発展は目覚ましく、最新のエビデンスをもとに順次その適応症は欧米を起点に広がりをみせています(対象患者の低リスク化および低年齢化や、機能不全に陥った外科用生体弁に対するTAVIによる再治療など)。
また、重症僧帽弁閉鎖不全症に対する経皮的僧帽弁接合不全修復術(TMVr: Transcatheter Mitral Valve Repair)も、多くのエビデンスが確立され今後の技術革新とともに更なる発展が期待される分野の一つです。これに加え、僧帽弁位においてはカテーテルを用いた生体弁留置術(TMVR: Transcatheter Mitral Valve Replacement)に対する研究開発も世界中で積極的に進められており、今後の製品化が待たれています。
その他にも、肺動脈弁に対するカテーテル治療は日本で徐々に広がり始めており、機能不全に陥った三尖弁に対するカテーテル治療も海外では臨床使用が開始され、弁膜症治療の低侵襲化の流れは今後日本においても加速することが予想されます。
また、弁膜症以外のSHDにおいては、心房細動に起因する脳卒中の予防として左心耳(LAA: Left Atrial Appendage)を閉鎖する経皮的左心耳閉鎖術や、脳梗塞の要因となり得る卵円孔開存(PFO: Patent Foramen Ovale) を閉鎖する経皮的卵円孔開存閉鎖術の国内導入が開始されています。
このように、SHDに対するインターベンション治療は心疾患領域における新たなカテーテル治療の柱として、今後の長期的な発展が期待されます。
整形外科手術

整形外科分野はいくつかの領域に分けられ、様々な医療機器が使用されています。
関節領域においては、変形関節症(OA)、関節リウマチ等が原因で変形し痛みを生じて生活にも影響が出ますが、手術によって人工関節を置換することで痛みの除去や関節可動域の改善が期待でき、生活の質の向上にも繋がります。上記の慢性疾患は勿論のこと、最近では大腿骨頸部骨折に対する治療でも人工股関節置換術が用いられるケースもあります。人工関節には日本でも適応症例の多い膝関節や股関節、その他にも肘関節、肩関節、足関節もあります。人工関節は比較的長期的に体内に置換され、いつも通りの生活をすることも想定されるため、インプラントの設置位置や設置角度が非常に重要になってきます。
骨折領域(トラウマ)においては、大腿骨・上腕骨・前腕骨での骨折が多く、骨接合用のプレート・髄内釘(骨の中に入れる棒状の固定器具)・スクリューなどを使用し、手術により直接骨を固定します。この外傷分野でも低侵襲の治療法が行われています。
脊椎領域(スパイン)においては、椎体骨折や椎間板ヘルニアなどに起因する神経圧迫や脊柱アライメントの異常に対し、固定術や矯正を目的として脊椎インプラント(スクリュー、ロッド、ケージ等)が使用されます。脊柱管内には脊髄や神経根が走行しており、これらの構造物への圧迫を除圧・矯正することで、上下肢のしびれや疼痛、運動障害などの神経症状の改善が期待されます。
スポーツ整形では膝靭帯再建・肩関節脱臼といったスポーツなどの激しい運動などにより、損傷した靭帯などを修復します。若年層の手術が多く、早期復帰を目指しますので整形外科用の内視鏡を用いて、低侵襲手技での靭帯再建が積極的に行われています。
また大きな骨の欠損に対しては人工骨が使用されます。特殊な整形外科領域としては小児整形外科があり、生まれつき変形した四肢を持つ子供に対して、矯正や骨の延長なども医療機器を使用することによって可能になっています。
近年では整形外科手術全般にNavigationという手術支援医療機器も広まってきており、より正確な手術が可能となりました。さらに海外では既に広まりつつありますが、日本においても2018年にロボティクス(手術支援ロボット)が導入され、臨床使用も開始されております。
これらは、患者様のCTデータや実際の骨の状況をもとに、コンピューターを用いて最適な設置位置・角度を算出してくれますので、術者はこの情報と照らし合わせて手術を進めることができ、より正確で安全な手術が可能になります。こういった手術は低侵襲にも繋がり、術後疼痛の低減や早期回復にも繋がり、患者様の満足度も非常に高くなっています。
内視鏡・内視鏡下外科手術

内視鏡機器は「早期診断」から「低侵襲治療」までを支える人体の中を見ることを目的とした医療機器です。体に挿入し、内部の様子を見ることができるだけでなく、治療や手術にも使われています。 主に光源・プロセッサー・モニター・内視鏡で構成されており、内視鏡は、胃や大腸などの消化管のほか、気管支、泌尿器、脳、関節といったさまざまな部位で活用されています。
一般的に「胃カメラ」と呼ばれる消化器内視鏡と「腹腔鏡」と呼ばれる外科用内視鏡に二分され、消化器内視鏡は主に上部消化管(食道・胃、十二指腸)、下部消化管(小腸・大腸)、気管支等の粘膜表層の病変観察や診断に用いられ、それぞれの部位に応じた専用設計の内視鏡が使用されます。特に大部分の検査を占める、上部消化管検査では技術の向上が目覚ましく、内視鏡の細径化による経鼻挿入、ハイビジョン画像による診断精度の向上や、特殊光技術による病変の特異的描出やAIによる画像解析技術の向上など診断方法も目まぐるしく発達しています。
また、消化管、呼吸器の深部診断には超音波内視鏡も使用されており、内視鏡の先に超音波画像装置が装着された内視鏡で、消化管壁の構造や膵臓、胆管、胆嚢、気管支やリンパ節などを詳細に観察する検査が行われ、通常の検査やCTなどでは難しい病期診断や正確な診断を行うことが可能となっています。
内視鏡的に行う治療では処置に適した内視鏡が使われる他、高周波電源装置や処置具の併用により多様な処置が行えます。ポリープ切除はEMRと呼ばれ内視鏡からスネアと呼ばれるリング状(輪っかの形状)のデバイスを挿入し高周波装置で電気的にポリープを切除する手技で、外来でも行える程に古くから普及しています。ESDは早期癌を内視鏡的に消化管の内腔から粘膜ごと一括切除する手技であり、胃、食道、大腸で保険収載され低侵襲な手技として標準的に行われています。
膵胆領域でも総胆管結石除去や胆道ドレナージ等が内視鏡的処置として行われ、バルーンカテーテル・バスケットカテーテル・砕石具・プラスチックステント等の処置具が用いられます。また食道ステント、十二指腸ステント、大腸ステントといった永久留置型メタリックステントなどの留置の際にも用いられます。カプセル内視鏡は超小型の内視鏡を錠剤の要領で飲み、口から肛門までの消化管を撮影して診断する製品です。従来の内視鏡ではアプローチ困難であった部位の観察に有効です。
内視鏡下外科手術は、5~10㎜位の小さな穴を数か所開け、腹腔内にCO2ガスを送り込みワーキングスペースを確保、そこに内視鏡や処置具を挿入してモニターを見ながら病巣を除去する手術を行います。開腹手術に比べ傷が小さく術後の痛みが少ない、回復が早いなどのメリットがあります。近年では肺、胃、大腸、膵臓、腎臓、前立腺、膀胱、子宮のように、難易度の高い手術にも適用範囲が広がっており一般的になってきています。
またより低侵襲と整容性の面から臍に25mm~30㎜位の一つの穴を開け手術する単孔式(Single port surgery)手術という治療法もあります。
内視鏡下外科手術ではモニター、気腹装置、内視鏡カメラ、録画装置、超音波凝固装置、高周波電気メス装置、エコーなどで構成された器械を使用します。処置具としてはラパロ鉗子、止血クリップ、持針器、サクションイリゲーター、臓器の吻合や縫合を行う為のステープラーや針糸、皮膚を通過する為のトロッカ―や創を保護するウンドリトラクター、他にも主な消耗品としてはガーゼ、ドレープ、ドレーン、回収バックなどがあります。
ロボット支援下内視鏡手術は手術支援ロボットを使用して3本の鉗子とカメラを一人で操作します。前立腺がんの手術においては最も広く行われており、3D拡大視野、関節機能鉗子、モーションスケーリング機能により腹腔鏡よりもより低侵襲で精緻な手術が可能です。現在では泌尿器科をはじめ消化器外科、呼吸器外科、婦人科、耳鼻咽喉科、心臓外科などで保険適用になり幅広い診療科で使用されております。
使用されるビデオカメラシステムの進歩は目覚ましく、市場にはハイビジョンをはじめ、立体視の出来る3Dシステム、ハイビジョン以上の高画質である、4K、8K、近赤外光を用いた血流や腫瘍の蛍光観察など様々な方法で画面を見ながら手術が行われています。その他、画像を映し出すために必要な、ビデオスコープ(硬性鏡)、光源装置、気腹装置などの機器類、狭い腹腔内で医師の手となる各種鉗子類、縫合器、吻合器、クリップ、ディスポ製品、血管や組織を縛ることなく切除可能な超音波凝固切開装置など内視鏡下外科手術に対応した特殊な電気メスも広く用いられています。
脳神経外科手術

脳神経外科手術は、脳・脊髄・末梢神経系およびそれに関連する血管、骨、筋肉など、神経系全般の疾患に対して外科的に治療を行う専門領域です。病変部が頭蓋内にある場合は、まず開頭術を実施します。頭皮と筋層を切開後、電動ドリルで頭蓋骨を開け、脳を包む硬膜を切開します。手術中は、手術用顕微鏡やナビゲーションシステムを用いて、正常な脳組織や血管を損傷しないよう慎重に進行します。止血にはバイポーラ凝固装置が使用され、閉頭時には成人にはチタン製プレート、小児には生体吸収性素材が用いられます。
疾患ごとの治療として、脳動脈瘤では破裂によるくも膜下出血を防ぐため、チタン製クリップで瘤の根元(ネック)を閉塞します。脳腫瘍では、超音波吸引装置(CUSA)や5-ALA蛍光ガイドを用い、安全に腫瘍を摘出します。特発性正常圧水頭症(iNPH)は、高齢者の歩行障害・認知症が改善可能なため注目されており、脳室腹腔シャントなどで脳脊髄液を排出します。最新のシャントバルブには圧調整機能やリモート制御機能が搭載されています。
さらに、神経内視鏡手術は低侵襲な選択肢として拡大しており、頭蓋内血腫、下垂体腫瘍、先天性水頭症の治療に活用されています。今後はロボット支援手術やAIによる画像解析も進み、安全性と正確性が著しく向上することが期待されています。手術機器市場では外資系企業が優勢ですが、ナビゲーションや内視鏡分野では日本企業の技術力も評価されています。
画像診断/治療装置・医療情報システム
医療現場における画像診断・治療装置は、疾患の早期発見や正確な診断、個別化治療計画の策定に不可欠です。代表的な装置にはCT、MRI、X線、超音波、PET-CTなどの核医学装置、リニアックやガンマナイフなどの放射線治療装置、陽子線治療装置があり、全身各部に対して高精度な画像情報を提供します。
PET-CTは全身のがん検出、マンモグラフィは乳がんの早期発見、IVRでは血管内治療をリアルタイム画像下で実施可能です。放射線治療ではIMRTやSRSにより、正常組織への影響を最小限に抑えた照射が実現されています。
AI技術の導入も進んでおり、CTでは肺結節や脳出血などの自動検出、MRIでは深層学習による画質向上と撮像時間の短縮が可能です。放射線治療では照射線量の最適化や自動輪郭抽出が精度向上に貢献しています。
画像データは3D再構成や定量解析が可能な専用ワークステーションで処理され、外科手術や放射線治療計画に活用されます。PACSにより院内各所でリアルタイムに画像を共有し、再検査の抑制やチーム医療の効率化を実現します。
周辺機器には造影剤注入器、術中ナビ、モニタ装置などがあり、医療スタッフとの連携によって安全性・正確性が最大化されます。近年では、術前・術中情報を統合したSmart ORやHybrid ORの導入も進んでいます。
また、画像診断装置はRISや電子カルテと連携し、院内のIT化とスマート医療を推進。今後はAIによる自動アラートやリスク予測が加わり、より個別化された高度医療が期待されています。
転職活動に
お困りですか?
- 自分の条件に合う求人がわからない
- 専門のコンサルタントに相談したい
- キャリアについて相談したい
医療機器転職.jpは医療機器業界専門の転職エージェントです。
業界出身のコンサルタントがあなたのキャリアをサポートします。
タグ
関連記事
転職相談
医療機器業界における転職やキャリア設計、
求人などまずはカジュアルにご相談を
承っております。
職種から探す
主要エリアから探す
領域検索